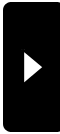機械加工業における協働ロボットの活用方法
2021年10月19日
1.はじめに
近年、様々なアプリケーションの開発により協働ロボットの需要が高まりつつあります。
機械加工業においてはまだまだ従来の産業用ロボットの活用が一般的ですが、今回は機械加工業における協働ロボットの活用方法について解説します。
2.統計から見る協働ロボットの現状
協働ロボットの需要は年々拡大傾向にあります。
2018年は世界の産業用ロボット出荷台数全体に占める割合は3%ほどです。
しかし伸び率では23%増となっており、2019年は産業用ロボット出荷台数に占める割合が4.8%となる1万8000台が出荷されています。
全体に締める割合としてはまだまだ少ないですが様々な付加機能が開発されており今後さらに協働ロボット市場は拡大していくと予想されます。
3.協働ロボットとは
産業用ロボットと協働ロボットの大きな違いは安全柵が不要であることです。
安全柵が不要であるため中小機械加工業において問題となるスペース不足の問題を解決しスペースを有効活用することが可能となります。
産業用ロボットと協働ロボットの活用イメージを以下に示します。
・産業用ロボット
①人間を超える生産性向上
②高速、高精度、重可搬
③設置スペース大(安全柵が必要)
④ロボット専門技術が必要
・協働ロボット
①人間のサポート
②ゆっくり、そこそこ、持てる物は軽い
③省スペース(安全柵不要)
④専門知識不要の簡単操作
上記をまとめると、
産業用ロボット→大量生産向け
協働ロボット→多品種少量生産向け
と言えるでしょう。
安全柵が不要で省スペース、それによるフレキシブルな活用が可能、専門的な技術が不要で簡易的な操作、それによる自社での低コストな導入、、、、
まさに協働ロボットは中小機械加工業における多品種少量生産に適したロボットであると言えます。
4.機械加工業における協働ロボットの具体的な活用方法
では具体的にどのように協働ロボットを活用するのでしょうか。
最新の協働ロボットは標準でカメラを搭載している物があります。
カメラが標準搭載されいるため従来、ロボットを画像認識を組み合わせた複雑なシステム構成が不要となり、アイディア次第でユーザーの要望に合わせた運用が可能になります。
従来のロボットと画像認識を組み合わせたシステムでは「キャリブレーション作業」が必須となり、これは専門の技術員が長時間かけて行う大変複雑な作業です。
標準でカメラを搭載した協働ロボットを活用することで、上記のようなキャリブレーション作業が不要となり、例えば以下のようなフレキシブルな運用が可能になります。
運用例
①午前中は旋盤AでワークBをロボットで100ケ加工する
②午後は旋盤BでワークEをロボットで100ケ加工する
③ロボットが加工をしている間、ロボットだと効率が悪い10ケ程度の小ロット品は人間が加工する
→ロボットと人間の「協働」で多品種少量生産対応
上記の運用例はカメラを搭載した協働ロボットの位置補正機能を活用し、フレキシブルに使いたい場所で使いたいときにロボットを使う、という運用を実現した例です。
何度も言いますが、このような運用を行うことはキャリブレーション作業が必要な従来のロボットでは実現不可能な運用方法です。
さらに、大手自動車メーカー等ではAGV(無人搬送車)と協働ロボットを組み合わせたシステムの活用を行っている企業もあります。
例えば、
AGVに協働ロボットを設置しておいて、自動倉庫から素材をロボット付きAGVで搬送して加工機の前まで持っていき、加工して、加工完了品はAGVで自動倉庫に自動で入庫する。
→AGVでは精度の良い位置決めが出来ないが画像認識の位置補正機能があるのである程度の位置決めでワーク投入できる
アイディア次第で様々な活用方法を検討することができます。
面白いアイディアとしては、フレキシブルに使いたい場所で使う運用方法のさらなるアイディアとして、加工機の加工完了ランプをカメラで見て、加工完了を確認しワークを取り出す、というような活用も可能です。
---------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはバイポーラステッピングモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
近年、様々なアプリケーションの開発により協働ロボットの需要が高まりつつあります。
機械加工業においてはまだまだ従来の産業用ロボットの活用が一般的ですが、今回は機械加工業における協働ロボットの活用方法について解説します。
2.統計から見る協働ロボットの現状
協働ロボットの需要は年々拡大傾向にあります。
2018年は世界の産業用ロボット出荷台数全体に占める割合は3%ほどです。
しかし伸び率では23%増となっており、2019年は産業用ロボット出荷台数に占める割合が4.8%となる1万8000台が出荷されています。
全体に締める割合としてはまだまだ少ないですが様々な付加機能が開発されており今後さらに協働ロボット市場は拡大していくと予想されます。
3.協働ロボットとは
産業用ロボットと協働ロボットの大きな違いは安全柵が不要であることです。
安全柵が不要であるため中小機械加工業において問題となるスペース不足の問題を解決しスペースを有効活用することが可能となります。
産業用ロボットと協働ロボットの活用イメージを以下に示します。
・産業用ロボット
①人間を超える生産性向上
②高速、高精度、重可搬
③設置スペース大(安全柵が必要)
④ロボット専門技術が必要
・協働ロボット
①人間のサポート
②ゆっくり、そこそこ、持てる物は軽い
③省スペース(安全柵不要)
④専門知識不要の簡単操作
上記をまとめると、
産業用ロボット→大量生産向け
協働ロボット→多品種少量生産向け
と言えるでしょう。
安全柵が不要で省スペース、それによるフレキシブルな活用が可能、専門的な技術が不要で簡易的な操作、それによる自社での低コストな導入、、、、
まさに協働ロボットは中小機械加工業における多品種少量生産に適したロボットであると言えます。
4.機械加工業における協働ロボットの具体的な活用方法
では具体的にどのように協働ロボットを活用するのでしょうか。
最新の協働ロボットは標準でカメラを搭載している物があります。
カメラが標準搭載されいるため従来、ロボットを画像認識を組み合わせた複雑なシステム構成が不要となり、アイディア次第でユーザーの要望に合わせた運用が可能になります。
従来のロボットと画像認識を組み合わせたシステムでは「キャリブレーション作業」が必須となり、これは専門の技術員が長時間かけて行う大変複雑な作業です。
標準でカメラを搭載した協働ロボットを活用することで、上記のようなキャリブレーション作業が不要となり、例えば以下のようなフレキシブルな運用が可能になります。
運用例
①午前中は旋盤AでワークBをロボットで100ケ加工する
②午後は旋盤BでワークEをロボットで100ケ加工する
③ロボットが加工をしている間、ロボットだと効率が悪い10ケ程度の小ロット品は人間が加工する
→ロボットと人間の「協働」で多品種少量生産対応
上記の運用例はカメラを搭載した協働ロボットの位置補正機能を活用し、フレキシブルに使いたい場所で使いたいときにロボットを使う、という運用を実現した例です。
何度も言いますが、このような運用を行うことはキャリブレーション作業が必要な従来のロボットでは実現不可能な運用方法です。
さらに、大手自動車メーカー等ではAGV(無人搬送車)と協働ロボットを組み合わせたシステムの活用を行っている企業もあります。
例えば、
AGVに協働ロボットを設置しておいて、自動倉庫から素材をロボット付きAGVで搬送して加工機の前まで持っていき、加工して、加工完了品はAGVで自動倉庫に自動で入庫する。
→AGVでは精度の良い位置決めが出来ないが画像認識の位置補正機能があるのである程度の位置決めでワーク投入できる
アイディア次第で様々な活用方法を検討することができます。
面白いアイディアとしては、フレキシブルに使いたい場所で使う運用方法のさらなるアイディアとして、加工機の加工完了ランプをカメラで見て、加工完了を確認しワークを取り出す、というような活用も可能です。
---------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはバイポーラステッピングモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by christopher at 17:02│Comments(0)